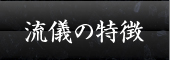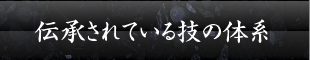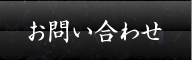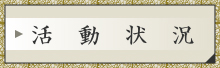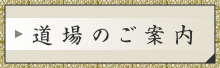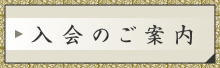HOME >> 由来

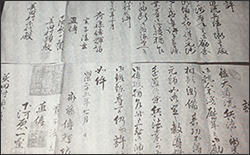 天道流の始祖は、
天道流の始祖は、斎藤判官伝鬼房(さいとうほうがんでんきぼう)である。
今から約440年前、伝鬼は常陸国(ひたちのくに)
井手(茨城県)に生まれ、
塚原卜傳(つかはらぼくでん)の門に入り
刀槍の術を学んだ。
大勢の門弟の中で群を抜いていたが、
技の未熟さを深く心に感じ、
鎌倉鶴岡八幡宮に百日参籠(さんろう)をなしました。
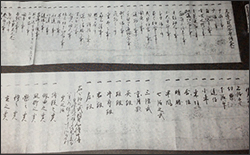 天正9年11月21日の満願の夜。
天正9年11月21日の満願の夜。夢の中に探し求めていた剣の妙技が記された
一軸の巻物を天から授かり、
誠にかなう妙技を得、一流を興してこれを『天流』と称し、
後に『天道流』と改めた。
これにより、諸国を巡り修行を重ね、
京都ではその剣名が上聞に達し、
『一刀三礼』の秘剣を天覧に供したと言われている。
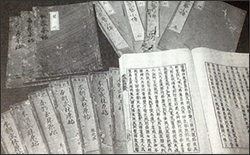 諸国修行を終えて郷里井出に居を構えて名声を馳せたが、
諸国修行を終えて郷里井出に居を構えて名声を馳せたが、霞神道流・真壁道無の門下、桜井大隈守と決闘、
射殺される。
その際に示した矢切の術を『一文字の乱』と言い、
今なお天道流の基本とされている。
伝鬼房の最期を見届けた弟子の小松一卜斎が
伝鬼房の実子、法玄にこの技を伝え、
法玄は二代目を継承し、その流儀は現在まで薙刀、
二刀、剣、鎖鎌、小太刀などとして伝承されている。